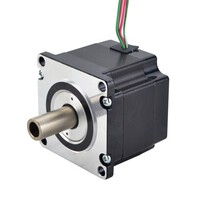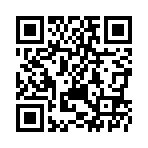3Dプリンターを熱溶解層方式(FDM)から光造形方式(SLA)にした人にありがちな失敗の原因
2022年06月30日
光造形方式(SLA)を使用する以前に熱溶解層方式(FDM)を使用していた方もいらっしゃるのではないでしょうか。FDMと勝手が違い、SLAで失敗してしまうという声を耳にします。
折角、3Dプリンターが好きで新しいプリンターに挑戦したのに上手くいかない…そんな悲しいことが起こってほしくないという願いを込めて、今回は「3Dプリンターを熱溶解層方式(FDM)から光造形方式(SLA)にした方にありがちな失敗の原因」についてお話しします。
1.FDMとSLAは似たようなものだと思っている
まず、FDMとSLAは全くの別物です。
扱う素材、必要な準備、造形物の出力の仕方、使用上の注意点など、まるで異なります。全くの別物であることをきちんと認識して使用してください。

2.空洞を作らずに出力してしまう
SLAには空洞が必要です。というのもレジンは薄い方が収縮が小さく、表面にひびが入りにくいです。中を空洞化させることによってレジンの無駄遣いを防ぐことも出来ます。
3.サポート材をFDMと同じように入れてしまう
サポート材はSLAとFDMに共通して必要とされるものですが、SLAにおいてFDMと全く同じようにサポート材を入れてしまうと失敗してしまうことが多いです。特に、サポート材が少ないと失敗します。うまくいかなかった場合はサポート材の入れ方を工夫してみてください。
4.FDMとSLAで同じ出力結果を期待してしまう
SLAのレジンは、FDMで使用するサーモプラスチックと違って熱や化学物質に強い反面、サーモプラスチックよりも脆いです。
そのため、FDMから始めた方はサーモプラスチックの様な強度を期待した結果、出力に失敗してしまいます。
5.IPAで洗浄すると長持ちすると思ってしまう
IPA(イソプロピルアルコール)とは、出力したものに付着している未硬化のレジンを洗浄するために使用するアルコールのことです。
IPAを出力したものを長持ちさせるために浸けると思っている方もいらっしゃるようです。
正しい使い方としては最大でも15分程度浸けるだけです。それ以上長くIPAに浸けてしまうと、せっかく作った作品の表面が変形したり、ひびが入ってしまうことがあるため気を付けてください。
そのほかIPAの使い方については別の記事でまとめましたので、そちらも確認してみてください。
レジン使用にあたって注意すべき7か条
6.初期層を利用し忘れる

FDMとSLAでは、出力のされ方が違います。具体的にどのように違うのかというと、FDMは上に層が重なっていくのに対し、SLAは下に層が積み重なっていきます。そうすると、FDMに慣れていた方には考えられないことが起きます。それは、出力中に出力物が落ちてしまうということです。これは非常に残念です。
そのような失敗が起きないよう、SLAでは初期層を利用します。初期層とは、出力物の土台のような物です。最初の何層かに紫外線をたっぷり当てることでプラットフォームにしっかりとレジンを定着させます。この初期層を作ることで出力物の落下を防げます。
7.3Dプリンターの設定をあまり調整しないで出力してしまう
3Dプリンターには様々な設定項目があります。これをデフォルトのままにしていませんか。もちろん、それで出力が上手くいっているのであれば良いのですが、あまり上手くいっていないという場合は設定値を変更してみてください。3Dプリンターの機種、使用する環境、使用するレジンによって最良の設定値は異なります。
最良の設定値を探ってみてください。
8.レジンの使用上の注意を見逃しがち
これはレジンに限らず、何かを使用するすべての場合に言えますが、使用上の注意をよく読んでから扱ってください。楽しく安全に3Dプリンターを使用しましょう。レジンは素手で触ってはいけません。「レジンの使用にあたって注意すべき七ヶ条」ではより詳しく触れているので是非熟読してみてください。最悪の場合、アレルギーを引き起こしてしまったりするので扱いには充分気を付けてください。特にペットやお子さんがいるおうちでは間違って直接触ってしまわぬよう保管場所にも充分気を付けてください。
9.インターネットの情報を鵜呑みにしてしまう
作ってみたい作品があった時、インターネットでデータの数値を取ってきたり3Dプリンターの設定を調べたりすることもあると思います。ですが、それは必ずしも正しいとは限りません。
ネット上にフェイクニュースが飛び交い、ポストトゥルースなどといった言葉も生まれる、世知辛い時代です。中には悪意ある偽情報もありますし、勘違いや誤った記載、自分の持っている3Dプリンターと合わない場合など、様々な心配があります。
----------------------------------------------------------------
skysmotor.comは遊星ギアボックスモータとBLDCモーターなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
折角、3Dプリンターが好きで新しいプリンターに挑戦したのに上手くいかない…そんな悲しいことが起こってほしくないという願いを込めて、今回は「3Dプリンターを熱溶解層方式(FDM)から光造形方式(SLA)にした方にありがちな失敗の原因」についてお話しします。
1.FDMとSLAは似たようなものだと思っている
まず、FDMとSLAは全くの別物です。
扱う素材、必要な準備、造形物の出力の仕方、使用上の注意点など、まるで異なります。全くの別物であることをきちんと認識して使用してください。

2.空洞を作らずに出力してしまう
SLAには空洞が必要です。というのもレジンは薄い方が収縮が小さく、表面にひびが入りにくいです。中を空洞化させることによってレジンの無駄遣いを防ぐことも出来ます。
3.サポート材をFDMと同じように入れてしまう
サポート材はSLAとFDMに共通して必要とされるものですが、SLAにおいてFDMと全く同じようにサポート材を入れてしまうと失敗してしまうことが多いです。特に、サポート材が少ないと失敗します。うまくいかなかった場合はサポート材の入れ方を工夫してみてください。
4.FDMとSLAで同じ出力結果を期待してしまう
SLAのレジンは、FDMで使用するサーモプラスチックと違って熱や化学物質に強い反面、サーモプラスチックよりも脆いです。
そのため、FDMから始めた方はサーモプラスチックの様な強度を期待した結果、出力に失敗してしまいます。
5.IPAで洗浄すると長持ちすると思ってしまう
IPA(イソプロピルアルコール)とは、出力したものに付着している未硬化のレジンを洗浄するために使用するアルコールのことです。
IPAを出力したものを長持ちさせるために浸けると思っている方もいらっしゃるようです。
正しい使い方としては最大でも15分程度浸けるだけです。それ以上長くIPAに浸けてしまうと、せっかく作った作品の表面が変形したり、ひびが入ってしまうことがあるため気を付けてください。
そのほかIPAの使い方については別の記事でまとめましたので、そちらも確認してみてください。
レジン使用にあたって注意すべき7か条
6.初期層を利用し忘れる

FDMとSLAでは、出力のされ方が違います。具体的にどのように違うのかというと、FDMは上に層が重なっていくのに対し、SLAは下に層が積み重なっていきます。そうすると、FDMに慣れていた方には考えられないことが起きます。それは、出力中に出力物が落ちてしまうということです。これは非常に残念です。
そのような失敗が起きないよう、SLAでは初期層を利用します。初期層とは、出力物の土台のような物です。最初の何層かに紫外線をたっぷり当てることでプラットフォームにしっかりとレジンを定着させます。この初期層を作ることで出力物の落下を防げます。
7.3Dプリンターの設定をあまり調整しないで出力してしまう
3Dプリンターには様々な設定項目があります。これをデフォルトのままにしていませんか。もちろん、それで出力が上手くいっているのであれば良いのですが、あまり上手くいっていないという場合は設定値を変更してみてください。3Dプリンターの機種、使用する環境、使用するレジンによって最良の設定値は異なります。
最良の設定値を探ってみてください。
8.レジンの使用上の注意を見逃しがち
これはレジンに限らず、何かを使用するすべての場合に言えますが、使用上の注意をよく読んでから扱ってください。楽しく安全に3Dプリンターを使用しましょう。レジンは素手で触ってはいけません。「レジンの使用にあたって注意すべき七ヶ条」ではより詳しく触れているので是非熟読してみてください。最悪の場合、アレルギーを引き起こしてしまったりするので扱いには充分気を付けてください。特にペットやお子さんがいるおうちでは間違って直接触ってしまわぬよう保管場所にも充分気を付けてください。
9.インターネットの情報を鵜呑みにしてしまう
作ってみたい作品があった時、インターネットでデータの数値を取ってきたり3Dプリンターの設定を調べたりすることもあると思います。ですが、それは必ずしも正しいとは限りません。
ネット上にフェイクニュースが飛び交い、ポストトゥルースなどといった言葉も生まれる、世知辛い時代です。中には悪意ある偽情報もありますし、勘違いや誤った記載、自分の持っている3Dプリンターと合わない場合など、様々な心配があります。
----------------------------------------------------------------
skysmotor.comは遊星ギアボックスモータとBLDCモーターなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
Posted by patricia at
15:48
│Comments(0)
ギヤードモーターの減速比とトルクについて
2022年06月25日
呼び減速比と実減速比の違いについて
一般的にカタログでの出力軸回転速度は、同期回転速度(回転磁界の回転速度)を呼び減速比で割った値を記載しております。よって、あくまで呼称回転速度であり、実際の回転速度とは異なります。
減速比選定の際の目安として使用する前提で記載されていますので、設計に際しては十分注意が必要となります。
例えば、モーター容量0.4kW―4極、カタログ呼び減速比1/5(実減速比は33/164)のギヤードモーターを検討するとします。使用地域は東日本で60Hzとします。60Hz地域で4極のモーターを回転させると同期回転速度は1800 r/minで、呼び減速比は1/5ですから出力軸回転数は360 r/minとなります。
この計算方法はあくまでも、目安の計算であり、実際には厳密な方法で出力軸回転数を導き出さなければなりません。
ここで先ほどの同期回転速度と呼び減速比が問題になってきます。
同期回転速度はモーターのすべりや抵抗などを考慮していない数値です。
また、呼び減速比は実際の歯車の組み合わせから求められた減速比ではないのです。
そこで、同期回転速度の代わりに定格回転速度を、呼び減速比の代わりに実減速比を用いて計算します。

定格回転速度とは負荷率が100%の時の回転速度となります。
この場合60Hzで回したモーターの定格回転速度は1690 r/minとなります。
負荷率が100%より小さければ、回転速度はもう少し速くなります。
あらためて、実際に近い回転速度を計算にて求めてみると、
1690 r/min X 33 / 164 = 340 r/min
となり、上記に求めた360 r/minと差異が出ます。
このように呼び減速比と実減速比には違いがあり、さらに同期回転速度と定格回転速度にも、大きな差異がありますので設計時には十分な配慮が必要となります。
最大許容トルクと許容トルクの違いについて
減速機部の出力トルクは、減速比が大きくなるとそれに比例して大きくなりますが、歯車の材質やその他の条件によって減速機部に掛けられる負荷トルクの大きさには限界があります。
この限界のトルクを最大許容トルクと呼んでいます。
許容トルクは、ギヤードモーターの出力軸に連続的に加えられるトルク値のことを表しています。
最大許容トルクはギヤードモーターの出力軸に加えることができる最大のトルク値のことを表しており、この二つの値は大きな違いがあります。
ギヤードモーターを選定するときの大きな要素になりますので、正確に覚えておきましょう。
減速比と出力トルクの関係について
減速比が大きくなると出力トルクも大きくなるのでしょうか?
従来使用していたコンベアで、今までよりとても重い商品を運ぶとします。
ギヤードモーターの減速比率を変更してトルクアップさせれば、運べるのでしょうか?
確か減速比が大きくなれば、出力トルクも大きくなるはずです。
ギヤードモーターの出力軸の許容トルクの求め方は↓
許容トルク(mN・m) =
モータートルク X 減速比 X 伝達効率 です。
つまり、減速機部の減速比が高いほどトルクもそれだけ出るということになります。

しかし、必ずしも計算上の値のトルクがかけられるというわけではありません。
実際には、ギヤードモーターの許容トルクが決まっていて負荷トルクには上限があります。
減速機部の中には歯車や、軸受などが使われており、その材質や大きさなどから、機械的な強度には限界があります。
それを踏まえて、許容トルクの値は決められています。
許容トルク以上のトルクをかけてしまったら破損するかというと、減速機部の設計では、機械的強度(安全率)を最大許容トルクの1.5~3倍程度とってあるので、短時間の過負荷で破損することは殆どありません。
ただし、使用頻度と時間によっては、寿命にかなりの影響を及ぼすことになります。
ですので、最大許容トルクを超えての使用は避けた方が良いということになります。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはリニアステッピングモータとハイブリッドステッピングモーターなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
一般的にカタログでの出力軸回転速度は、同期回転速度(回転磁界の回転速度)を呼び減速比で割った値を記載しております。よって、あくまで呼称回転速度であり、実際の回転速度とは異なります。
減速比選定の際の目安として使用する前提で記載されていますので、設計に際しては十分注意が必要となります。
例えば、モーター容量0.4kW―4極、カタログ呼び減速比1/5(実減速比は33/164)のギヤードモーターを検討するとします。使用地域は東日本で60Hzとします。60Hz地域で4極のモーターを回転させると同期回転速度は1800 r/minで、呼び減速比は1/5ですから出力軸回転数は360 r/minとなります。
この計算方法はあくまでも、目安の計算であり、実際には厳密な方法で出力軸回転数を導き出さなければなりません。
ここで先ほどの同期回転速度と呼び減速比が問題になってきます。
同期回転速度はモーターのすべりや抵抗などを考慮していない数値です。
また、呼び減速比は実際の歯車の組み合わせから求められた減速比ではないのです。
そこで、同期回転速度の代わりに定格回転速度を、呼び減速比の代わりに実減速比を用いて計算します。

定格回転速度とは負荷率が100%の時の回転速度となります。
この場合60Hzで回したモーターの定格回転速度は1690 r/minとなります。
負荷率が100%より小さければ、回転速度はもう少し速くなります。
あらためて、実際に近い回転速度を計算にて求めてみると、
1690 r/min X 33 / 164 = 340 r/min
となり、上記に求めた360 r/minと差異が出ます。
このように呼び減速比と実減速比には違いがあり、さらに同期回転速度と定格回転速度にも、大きな差異がありますので設計時には十分な配慮が必要となります。
最大許容トルクと許容トルクの違いについて
減速機部の出力トルクは、減速比が大きくなるとそれに比例して大きくなりますが、歯車の材質やその他の条件によって減速機部に掛けられる負荷トルクの大きさには限界があります。
この限界のトルクを最大許容トルクと呼んでいます。
許容トルクは、ギヤードモーターの出力軸に連続的に加えられるトルク値のことを表しています。
最大許容トルクはギヤードモーターの出力軸に加えることができる最大のトルク値のことを表しており、この二つの値は大きな違いがあります。
ギヤードモーターを選定するときの大きな要素になりますので、正確に覚えておきましょう。
減速比と出力トルクの関係について
減速比が大きくなると出力トルクも大きくなるのでしょうか?
従来使用していたコンベアで、今までよりとても重い商品を運ぶとします。
ギヤードモーターの減速比率を変更してトルクアップさせれば、運べるのでしょうか?
確か減速比が大きくなれば、出力トルクも大きくなるはずです。
ギヤードモーターの出力軸の許容トルクの求め方は↓
許容トルク(mN・m) =
モータートルク X 減速比 X 伝達効率 です。
つまり、減速機部の減速比が高いほどトルクもそれだけ出るということになります。

しかし、必ずしも計算上の値のトルクがかけられるというわけではありません。
実際には、ギヤードモーターの許容トルクが決まっていて負荷トルクには上限があります。
減速機部の中には歯車や、軸受などが使われており、その材質や大きさなどから、機械的な強度には限界があります。
それを踏まえて、許容トルクの値は決められています。
許容トルク以上のトルクをかけてしまったら破損するかというと、減速機部の設計では、機械的強度(安全率)を最大許容トルクの1.5~3倍程度とってあるので、短時間の過負荷で破損することは殆どありません。
ただし、使用頻度と時間によっては、寿命にかなりの影響を及ぼすことになります。
ですので、最大許容トルクを超えての使用は避けた方が良いということになります。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはリニアステッピングモータとハイブリッドステッピングモーターなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
Posted by patricia at
15:06
│Comments(0)
誘導モータの効率規制
2022年06月20日
○三相誘導モータの効率と規格
三相交流の入力に力率を掛けると有効電力となります。この有効電力がモータに入力されるエネルギーです。この入力エネルギーに対する出力の比を「効率」といいます。効率は、モータ内部の電気的・機械的損失が小さいほど高くなります。
モータの効率基準は、2000年にJISにより定められました。
国際標準として、2007年に効率の算定方法の規定が定まり、2008年にIEC60034-30(単一速度三相かご形誘導電動機の効率クラス)が制定されました。

○効率クラスとは
効率クラスは、効率基準値をクラスで分類したもので、IE4(スーパープレミアム効率)、IE3(プレミアム効率)、IE2(高効率)及びIE1(標準効率)の4段階です。この効率クラス(IEx)は、モータの銘板に記載されます。

○各国の動向
米国では、エネルギー政策法の制定により、2002年からモータの定格銘板に全負荷効率値と適合証明番号の記載が義務付けられました。
欧州では、2011年以降IE2レベルを満たし、2017年にはIE3レベルを満たすか又はIE2レベルにインバータを搭載する義務化を定めました。
中国では、2011年に効率基準値を定めました。
○シリーズ名と効率
例えば、日立産機のザ・モートルNeo100シリーズや、三菱電機のスーパーラインシリーズSF-JR型は標準効率(IE1)相当です。
-----------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはステッピングモータエンコーダとリニアステッピングモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
三相交流の入力に力率を掛けると有効電力となります。この有効電力がモータに入力されるエネルギーです。この入力エネルギーに対する出力の比を「効率」といいます。効率は、モータ内部の電気的・機械的損失が小さいほど高くなります。
モータの効率基準は、2000年にJISにより定められました。
国際標準として、2007年に効率の算定方法の規定が定まり、2008年にIEC60034-30(単一速度三相かご形誘導電動機の効率クラス)が制定されました。

○効率クラスとは
効率クラスは、効率基準値をクラスで分類したもので、IE4(スーパープレミアム効率)、IE3(プレミアム効率)、IE2(高効率)及びIE1(標準効率)の4段階です。この効率クラス(IEx)は、モータの銘板に記載されます。

○各国の動向
米国では、エネルギー政策法の制定により、2002年からモータの定格銘板に全負荷効率値と適合証明番号の記載が義務付けられました。
欧州では、2011年以降IE2レベルを満たし、2017年にはIE3レベルを満たすか又はIE2レベルにインバータを搭載する義務化を定めました。
中国では、2011年に効率基準値を定めました。
○シリーズ名と効率
例えば、日立産機のザ・モートルNeo100シリーズや、三菱電機のスーパーラインシリーズSF-JR型は標準効率(IE1)相当です。
-----------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはステッピングモータエンコーダとリニアステッピングモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
Posted by patricia at
16:19
│Comments(0)
三相交流の結線を切り替えるスターデルタ始動
2022年06月14日
○結線の切り替えで電圧を変化させる
三相誘導モータのステータの一次巻線(固定子のコイル)は、モータは、電力会社からの三相に応じて3つの端子があります。全電圧では、各端子を頂点とするデルタ型に接続します(デルタ結線)。
この3つの端子をY字(の上下反転)の各端部に接続するスター結線とすると、コイルへの電圧は、デルタ結線の約1/1.73(約58%)となります。この分母は√3です。
スター(Y)型の結線で始動をすると、電圧を押さえて始動電流を小さくすることができます。そして、加速後にデルタ(Δ)型の結線に切り替えることで、全電圧で運転します。

○スターデルタ始動のメリット
スターデルタ始動では、結線を切り替えるのみで、始動時の供給電圧を低下させ、始動電流の悪影響を除去することができます。スターデルタ始動は、対応する電磁開閉器というスイッチの一機能に組み込まれていることが多いです。また、モータに外付けする自動スターデルタ始動器もあります。

○スターデルタ始動のデメリットと対策
トルクは電圧の二乗に比例するため、スター結線で電圧が1/√3となると、トルクは1/3となります。三相誘導電動機は始動トルクが小さく、さらに1/3となると、大きな加速トルクを必要とする負荷に対応できないこともあります。この場合、より出力の大きいモータを選定することで対応します。
----------------------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはユニポーラステッピングモータとステッピングモータエンコーダなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
三相誘導モータのステータの一次巻線(固定子のコイル)は、モータは、電力会社からの三相に応じて3つの端子があります。全電圧では、各端子を頂点とするデルタ型に接続します(デルタ結線)。
この3つの端子をY字(の上下反転)の各端部に接続するスター結線とすると、コイルへの電圧は、デルタ結線の約1/1.73(約58%)となります。この分母は√3です。
スター(Y)型の結線で始動をすると、電圧を押さえて始動電流を小さくすることができます。そして、加速後にデルタ(Δ)型の結線に切り替えることで、全電圧で運転します。

○スターデルタ始動のメリット
スターデルタ始動では、結線を切り替えるのみで、始動時の供給電圧を低下させ、始動電流の悪影響を除去することができます。スターデルタ始動は、対応する電磁開閉器というスイッチの一機能に組み込まれていることが多いです。また、モータに外付けする自動スターデルタ始動器もあります。

○スターデルタ始動のデメリットと対策
トルクは電圧の二乗に比例するため、スター結線で電圧が1/√3となると、トルクは1/3となります。三相誘導電動機は始動トルクが小さく、さらに1/3となると、大きな加速トルクを必要とする負荷に対応できないこともあります。この場合、より出力の大きいモータを選定することで対応します。
----------------------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはユニポーラステッピングモータとステッピングモータエンコーダなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
Posted by patricia at
15:07
│Comments(0)
3Dフードプリンターのメリット
2022年06月08日
食品の自由度の向上
3Dフードプリンターは、樹脂造形などを行う従来の3Dプリンターと同じように、複数の材料を使って立体的に積層を行うなどして、自由度の高い食品を製造できます。
チョコレート細工のようにデザイン性も重視したスイーツを作る場合でも、3Dフードプリンターであれば、人間の手では造形が難しい食品でも製造が可能になります。
また、機械による製造のため、同じ原材料や出力設定、互換性のある3Dフードプリンターがあれば、全く同じレシピの再現も期待できます。

栄養価を調整した食品の製造
3Dフードプリンターは、使用する材料のタンパク質・ビタミン・ミネラル・糖分などの量を調整することができます。これにより、高齢者や病院での患者など、決められた食事しか取れない方に対して、健康面に配慮した食事を提供できます。
食品ロスの低減
3Dフードプリンターは、使用する材料に野菜のくずや、虫などを利用できるとの考えもあります。一般的には廃棄される材料や、見た目の問題で食材として利用されないようなモノを活用することで、食品ロスの低減が期待できます。

古くなったパンやフルーツの皮をペースト状にして、3Dフードプリンターで印刷したものをオーブンで焼き、水分が残らないように乾燥させれば、長期保存が可能な食品が得られるとの事例もあります。
将来、3Dフードプリンターが普及すれば、廃棄される食材が減り、SDGs(持続可能な開発目標)の飢餓をゼロにするなどの目標に貢献できるかもしれません。
-----------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはリニアステッピングモータと中空ステッピングモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
3Dフードプリンターは、樹脂造形などを行う従来の3Dプリンターと同じように、複数の材料を使って立体的に積層を行うなどして、自由度の高い食品を製造できます。
チョコレート細工のようにデザイン性も重視したスイーツを作る場合でも、3Dフードプリンターであれば、人間の手では造形が難しい食品でも製造が可能になります。
また、機械による製造のため、同じ原材料や出力設定、互換性のある3Dフードプリンターがあれば、全く同じレシピの再現も期待できます。

栄養価を調整した食品の製造
3Dフードプリンターは、使用する材料のタンパク質・ビタミン・ミネラル・糖分などの量を調整することができます。これにより、高齢者や病院での患者など、決められた食事しか取れない方に対して、健康面に配慮した食事を提供できます。
食品ロスの低減
3Dフードプリンターは、使用する材料に野菜のくずや、虫などを利用できるとの考えもあります。一般的には廃棄される材料や、見た目の問題で食材として利用されないようなモノを活用することで、食品ロスの低減が期待できます。

古くなったパンやフルーツの皮をペースト状にして、3Dフードプリンターで印刷したものをオーブンで焼き、水分が残らないように乾燥させれば、長期保存が可能な食品が得られるとの事例もあります。
将来、3Dフードプリンターが普及すれば、廃棄される食材が減り、SDGs(持続可能な開発目標)の飢餓をゼロにするなどの目標に貢献できるかもしれません。
-----------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはリニアステッピングモータと中空ステッピングモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
Posted by patricia at
16:19
│Comments(0)
金属3Dプリンターで造形するメリット
2022年06月01日
金属3Dプリンターのメリットは以下のとおりです。
複雑な形状も造形可
金属3Dプリンターは、さまざまな形状のものを製造できます。鋳造・鍛造・切削といったこれまでの製法では製作ができない、あるいは非常に難しい複雑な形状も造形可能です。DfAM(=Design for Additive Manufacturing、積層造形ならではの設計) を取り入れることで、これまでにない新製品の開発も可能になります。
また、金属3Dプリンターを用いることで、設計図や金型が残っていない部品を造形する「リバースエンジニアリング」も可能です。

短納期で試作品を納入できる
短納期での試作品納入(ラピッドプロトタイピング)も可能です。また、細かな設計変更などにも柔軟に対応できます。
作業時間とコストの削減が可能
積層造形ならではの一体造形により、部品数の削減はもちろんのこと、部品の溶接やロウ付けも不要です。また、トポロジー最適化(強度を損なわずに軽量化を実現) によって部品の軽量化も図れます。

加えて、コンフォーマル流路で金型の冷却時間の短縮化・冷却効率の上昇が、ラティス構造によってヒートシンク/熱交換器の排熱性向上が期待できます。これにより、製造にかかる作業時間とコストの削減や、機能性の向上が見込めるでしょう。
金属3Dプリンターが稼働している間は監視の必要もないため(最近は装置のモニタリング機能も充実してきている)、人的リソースの節約にもつながります。
多品種のものを大量に造形可能
金属3Dプリンターでは、ワンバッチで多品種のものを造形するマスカスタマイゼーションが可能です。小型品であればさまざまな種類のものでも一度に大量に造形でき、さらなるコスト削減にもつながるでしょう。
--------------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはリニアステッピングモータとCNCステッピングモーターなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
複雑な形状も造形可
金属3Dプリンターは、さまざまな形状のものを製造できます。鋳造・鍛造・切削といったこれまでの製法では製作ができない、あるいは非常に難しい複雑な形状も造形可能です。DfAM(=Design for Additive Manufacturing、積層造形ならではの設計) を取り入れることで、これまでにない新製品の開発も可能になります。
また、金属3Dプリンターを用いることで、設計図や金型が残っていない部品を造形する「リバースエンジニアリング」も可能です。

短納期で試作品を納入できる
短納期での試作品納入(ラピッドプロトタイピング)も可能です。また、細かな設計変更などにも柔軟に対応できます。
作業時間とコストの削減が可能
積層造形ならではの一体造形により、部品数の削減はもちろんのこと、部品の溶接やロウ付けも不要です。また、トポロジー最適化(強度を損なわずに軽量化を実現) によって部品の軽量化も図れます。

加えて、コンフォーマル流路で金型の冷却時間の短縮化・冷却効率の上昇が、ラティス構造によってヒートシンク/熱交換器の排熱性向上が期待できます。これにより、製造にかかる作業時間とコストの削減や、機能性の向上が見込めるでしょう。
金属3Dプリンターが稼働している間は監視の必要もないため(最近は装置のモニタリング機能も充実してきている)、人的リソースの節約にもつながります。
多品種のものを大量に造形可能
金属3Dプリンターでは、ワンバッチで多品種のものを造形するマスカスタマイゼーションが可能です。小型品であればさまざまな種類のものでも一度に大量に造形でき、さらなるコスト削減にもつながるでしょう。
--------------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはリニアステッピングモータとCNCステッピングモーターなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
Posted by patricia at
12:24
│Comments(0)