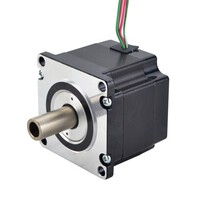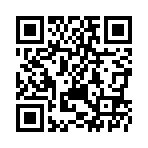協働ロボット誕生の背景
2022年02月23日
まず産業用ロボットの歴史についてですが、1954年にアメリカのジョージ・C・デボル氏がプレイバック・ロボットの概念を現し、特許を出願したのが始まりです。そして後の1962年にユニメーション社が“ユニメート”を、AMF社が“バーサトラン”と言う産業用ロボットをそれぞれ発表し、産業用ロボットが世の中に出回り始めました。1968年には川崎重工がユニメーション社と技術提携して輸入販売を開始、翌年に同社が国産初の産業ロボットの販売を開始し、日本の産業用ロボットの歴史がスタートしました。当時は高度経済成長期で人手不足が社会問題となっており、作業を効率化することで労働力を補う手段として産業用ロボットのニーズが高まっていきました。しかしながら産業用ロボットはコストが高く、単一の作業しか対応できませんでした(正確には、扱いが難しく汎用性を持たせることができなかった)。
また、1981年には国内初の産業用ロボットによる死亡災害が発生したこともあり、安全関係法令の整備が進み安全柵の中で隔離して使用することが義務付けられました。 こうした特性から、従来の産業用ロボットは主に自動車産業などの大規模製造業においてのみ導入が進められ、範囲は極めて限定的でした。
現在、少子高齢化に伴う人手不足が深刻な社会問題となっております。 また、情報化社会の進展により消費の多様化・多品種少量生産のニーズが高まっています。このような時代においては、従来の産業用ロボットではなく、労働力の補完や多品種少量生産を実現できる新しいタイプのロボットである“協働ロボット”が求められるようになりました。
-------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはクローズドループステッピングモータとステッピングモータエンコーダなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
また、1981年には国内初の産業用ロボットによる死亡災害が発生したこともあり、安全関係法令の整備が進み安全柵の中で隔離して使用することが義務付けられました。 こうした特性から、従来の産業用ロボットは主に自動車産業などの大規模製造業においてのみ導入が進められ、範囲は極めて限定的でした。
現在、少子高齢化に伴う人手不足が深刻な社会問題となっております。 また、情報化社会の進展により消費の多様化・多品種少量生産のニーズが高まっています。このような時代においては、従来の産業用ロボットではなく、労働力の補完や多品種少量生産を実現できる新しいタイプのロボットである“協働ロボット”が求められるようになりました。
-------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはクローズドループステッピングモータとステッピングモータエンコーダなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
Posted by patricia at
15:18
│Comments(0)
3Dプリンターの基本的な素材
2022年02月17日
3Dプリンターで使われる素材と聞くと、樹脂をイメージする方がきっと多いのではないでしょうか?でも実は樹脂以外にもたくさんの素材が使われているんです。よく使われる素材としては以下のようなものがあります。
・ABS
電化製品などに使われる素材です。塗装がしやすくて衝撃にも強いのが特徴です。
・ポリ乳酸(PLA)
植物由来の乳酸から作られるプラスチックです。初心者が使うのに向いている素材です。
・PPライク
光硬化性アクリル樹脂の一つです。高精細プリンターでよく用いられます。
・ゴムライク
ゴムのような柔軟性を持つ素材です。
・ポリカーボネート
耐久性が抜群で、精密機器や自動車部品によく使われます。耐熱性にも優れています。
・ポリプロピレン
柔軟ながら強度があるプラスチックです。酸やアルカリや油などの薬品に強いという特徴があります。
・Ultem
耐久性や耐熱性、耐薬品性に優れているプラスチックで、なんと航空機などの部品にも使われています。
・石膏
硫酸カルシウムが成分の素材です。着色が可能とあって、模型に使われることがあります。
・金属
チタンや銅やアルミなどの金属も使用されます。金属製のものは試作品を作るためではなく、そのまま最終製品として利用できるとして注目されています。
・ウッドライク
木の粉とナイロンの粉末を混ぜて作った素材です。木のような質がありますが、実は日本のオリジナル素材です。
3Dプリンターではこのようにいろいろな素材を使って立体物を作っていきます。「こんなに種類があるんだ!」と驚かれたのではないでしょうか。
ちなみにFDMやマテリアルジェッティングなどの造形方式で使う素材は「フィラメント」と呼ばれています。フィラメントは普通のプリンターでいうところのインクのようなものです。
3Dプリンターの実物を見たことがある人は、プリンターの隣にリールに巻き付けてあるカラフルなケーブルのようなものを見たことがあるかもしれませんね。あれがフィラメントです。
------------------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはユニポーラステッピングモータと平行軸ギヤードモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
・ABS
電化製品などに使われる素材です。塗装がしやすくて衝撃にも強いのが特徴です。
・ポリ乳酸(PLA)
植物由来の乳酸から作られるプラスチックです。初心者が使うのに向いている素材です。
・PPライク
光硬化性アクリル樹脂の一つです。高精細プリンターでよく用いられます。
・ゴムライク
ゴムのような柔軟性を持つ素材です。
・ポリカーボネート
耐久性が抜群で、精密機器や自動車部品によく使われます。耐熱性にも優れています。
・ポリプロピレン
柔軟ながら強度があるプラスチックです。酸やアルカリや油などの薬品に強いという特徴があります。
・Ultem
耐久性や耐熱性、耐薬品性に優れているプラスチックで、なんと航空機などの部品にも使われています。
・石膏
硫酸カルシウムが成分の素材です。着色が可能とあって、模型に使われることがあります。
・金属
チタンや銅やアルミなどの金属も使用されます。金属製のものは試作品を作るためではなく、そのまま最終製品として利用できるとして注目されています。
・ウッドライク
木の粉とナイロンの粉末を混ぜて作った素材です。木のような質がありますが、実は日本のオリジナル素材です。
3Dプリンターではこのようにいろいろな素材を使って立体物を作っていきます。「こんなに種類があるんだ!」と驚かれたのではないでしょうか。
ちなみにFDMやマテリアルジェッティングなどの造形方式で使う素材は「フィラメント」と呼ばれています。フィラメントは普通のプリンターでいうところのインクのようなものです。
3Dプリンターの実物を見たことがある人は、プリンターの隣にリールに巻き付けてあるカラフルなケーブルのようなものを見たことがあるかもしれませんね。あれがフィラメントです。
------------------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはユニポーラステッピングモータと平行軸ギヤードモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
Posted by patricia at
14:58
│Comments(0)
協働ロボットを導入するデメリット
2022年02月11日
ロボットだけで作業するのは難しい
協働ロボットはあくまで人の作業をサポートするような使われ方に適しているロボットなので、作業工程を全て自動化するような用途には適していません。
無人での作業は難しいかもしれませんが、協働ロボットと人間の強みをうまく掛け合わせることによって作業を効率化することができます。
ロボットの専門知識が必要
協働ロボットを実際に導入する場合は、定期点検やメンテナンス、誤作動への対応といった専門知識を持った人材が必要になります。
またロボットの動きをプログラムする「ティーチング」と呼ばれる作業ができる人材も必要となります。そのため長期的な視点を持って協働ロボットを扱える人材の育成を進めていく必要があるでしょう。
誤作動の可能性がある
ロボットや機械には誤操作や故障が発生するリスクが常にあります。
たとえばプログラムの設定を間違え誤作動を起こしてしまったり、災害時などに電源供給システムなどのトラブルが発生した場合の対処法を事前にシミュレーションしておく必要があります。
--------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはブラシレスDCモータとリニアステッピングモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
協働ロボットはあくまで人の作業をサポートするような使われ方に適しているロボットなので、作業工程を全て自動化するような用途には適していません。
無人での作業は難しいかもしれませんが、協働ロボットと人間の強みをうまく掛け合わせることによって作業を効率化することができます。
ロボットの専門知識が必要
協働ロボットを実際に導入する場合は、定期点検やメンテナンス、誤作動への対応といった専門知識を持った人材が必要になります。
またロボットの動きをプログラムする「ティーチング」と呼ばれる作業ができる人材も必要となります。そのため長期的な視点を持って協働ロボットを扱える人材の育成を進めていく必要があるでしょう。
誤作動の可能性がある
ロボットや機械には誤操作や故障が発生するリスクが常にあります。
たとえばプログラムの設定を間違え誤作動を起こしてしまったり、災害時などに電源供給システムなどのトラブルが発生した場合の対処法を事前にシミュレーションしておく必要があります。
--------------------------------------------------------------------------
skysmotor.comはブラシレスDCモータとリニアステッピングモータなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
Posted by patricia at
15:24
│Comments(0)
多関節ロボットのメリット
2022年02月07日
作業効率が向上する
産業用ロボットを導入することで生産ラインにおける作業効率を上げることが可能です。
例えば、ロボットは営業時間外でも24時間365日稼働できるため、生産性を維持しながら作業員の時間外労働を減らすことが可能です。
自由度が高い動きができる
多関節ロボットは多関節(多軸)構造によって人間の腕のように自由度が高い動きを実現できます。そのため従来のロボットでは困難であった熟練工のような繊細な技術も再現可能です。
熟練工の技術をロボットで再現することで、少子高齢化などによる技術継承問題を解消することができるというメリットがあります。
可動範囲が広く設置面積が少ない
多関節ロボットは可動範囲に対する設置面積が少ないため省スペースで設置できる点が魅力です。また垂直多関節ロボットであればアームを360度回転させることも可能です。
限られたスペースしかない工場内であっても、製造ラインのレイアウトに合わせて柔軟に設置できる点がメリットです。
汎用性が高い
多関節ロボットの先端部分にある「エンドエフェクタ」は作業内容に応じて付け替えることができます。そのため同じロボットを使って搬送から組み立て、溶接などの目的に応じた作業をすることも可能です。
--------------------------------------------------------------
skysmotor.comはユニポーラステッピングモータとモータドライバなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
産業用ロボットを導入することで生産ラインにおける作業効率を上げることが可能です。
例えば、ロボットは営業時間外でも24時間365日稼働できるため、生産性を維持しながら作業員の時間外労働を減らすことが可能です。
自由度が高い動きができる
多関節ロボットは多関節(多軸)構造によって人間の腕のように自由度が高い動きを実現できます。そのため従来のロボットでは困難であった熟練工のような繊細な技術も再現可能です。
熟練工の技術をロボットで再現することで、少子高齢化などによる技術継承問題を解消することができるというメリットがあります。
可動範囲が広く設置面積が少ない
多関節ロボットは可動範囲に対する設置面積が少ないため省スペースで設置できる点が魅力です。また垂直多関節ロボットであればアームを360度回転させることも可能です。
限られたスペースしかない工場内であっても、製造ラインのレイアウトに合わせて柔軟に設置できる点がメリットです。
汎用性が高い
多関節ロボットの先端部分にある「エンドエフェクタ」は作業内容に応じて付け替えることができます。そのため同じロボットを使って搬送から組み立て、溶接などの目的に応じた作業をすることも可能です。
--------------------------------------------------------------
skysmotor.comはユニポーラステッピングモータとモータドライバなどを販売している専門的なオンラインサプライヤーです。お客様に競争力のある価格、または効率的なサービスを提供しております。
Posted by patricia at
15:32
│Comments(0)